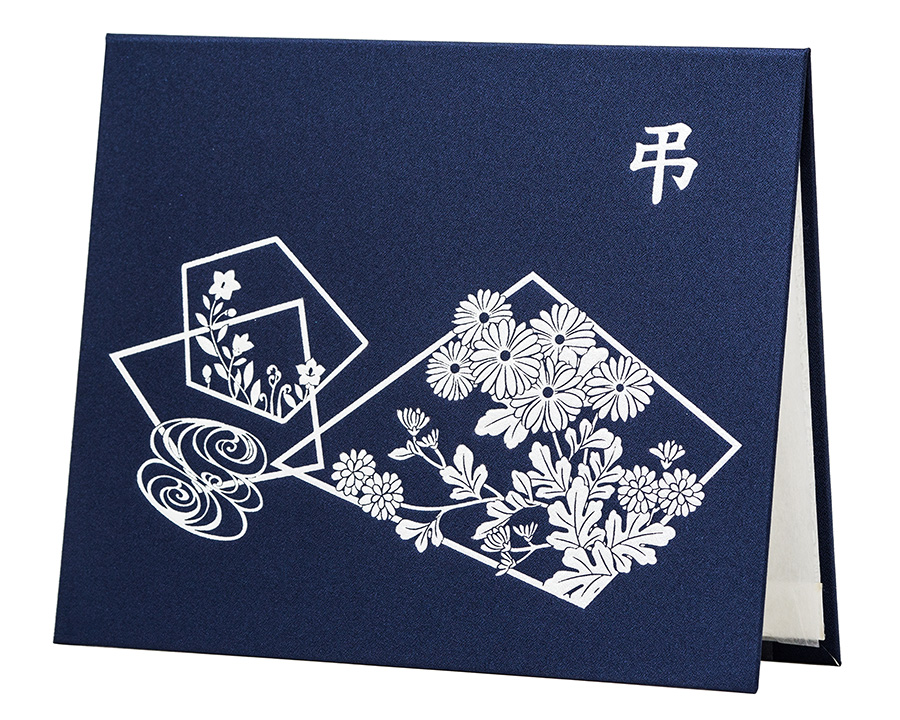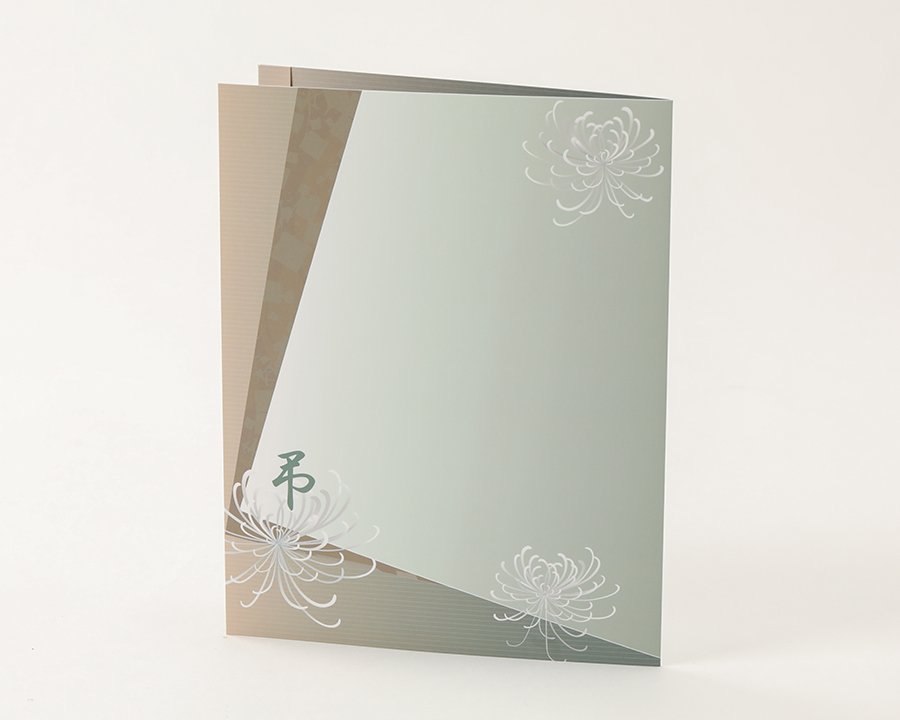弔電のお礼状・お返しのマナーとは?はがきやメールでの対応、会社への対応も紹介
#お悔やみ・葬儀・法事・法要
公開日:
更新日:

目次
・弔電のお礼・お返しに関する基本マナー
・会社から弔電をいただいた場合のお礼・お返し
・弔電のお礼状を作成する際の注意点
・メールで弔電のお礼を送る場合
・連名での弔電のお礼状・お返しはどうする?
・弔電のお礼状の文例【個人宛】【会社宛】
・はがきや手紙、メールなどで弔電のお礼を伝えよう
そこで今回は、弔電のお礼・お返しに関する基本マナー、会社から弔電をいただいた場合の対応について解説します。また、弔電のお礼状作成時に押さえておきたい注意点や文例、メールでのお礼の送り方についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
弔電のお礼・お返しに関する基本マナー
弔電を受け取った場合、一般的にはお礼状を出すのがマナーです。悲しみに寄り添っていただいたことに対し、相手へ感謝の気持ちを伝えましょう。ここからは、弔電のお礼状を出すときに知っておきたい基本マナーを解説します。
◇弔電のお礼状を送るのはいつまで?
弔電のお礼状の発送は、葬儀から1週間以内を目安に行います。なぜなら、お礼状には、葬儀がつつがなく終わったことを相手に知らせる役割もあるからです。
ときには、弔電の差出人の連絡先がわからないケースもあります。そういう場合は、お礼状を出さなくても失礼にはあたりません。無理に相手の連絡先を調べる必要はなく、口頭でのお礼のみで構いません。
◇弔電のお礼は手紙やはがきで
弔電のお礼は、相手方に出向いて直接伝えるのが正式な作法です。しかし、近年ではお礼状を郵送するのが一般的になっています。
メールやメッセンジャーアプリで弔電のお礼をするのは、相手から「フランクすぎる」と思われるおそれがあるため、避けたほうが無難です。ただし、普段からメールのみでやりとりをしている仕事関係の方などに対しては、ビジネスメールでお礼を伝えても悪い印象にはならないでしょう。
◇特に親しい相手なら、電話でお礼を伝えてもよい
親族や友人など、弔電の差出人と親しい間柄の場合は、電話でお礼を伝えてもよいでしょう。相手との関係性を踏まえて、お礼の方法を選択しましょう。
電話でお礼を伝えるなら、葬儀の翌日に行うのが適切です。お礼状を送るタイミングとは異なるため、注意してください。
◇お返しの品は基本的には不要
弔電をいただいた際、お返しの品を送るべきか悩む方もいるかもしれません。しかし、相手に気を遣わせてしまうため、基本的にお返しの品は不要です。
ただし、弔電とは別に香典・供物・供花を送ってくださった方には、お礼の品を用意し、四十九日(もしくは三十五日)の法要を終えた忌明けにお返ししましょう。お礼の品の値段は、いただいた品の値段の3分の1から半分ほどを目安にします。
■会社から弔電をいただいた場合のお礼・お返し
ここでは、会社から弔電をいただいた際のお礼・お返しについて説明します。◇弔電のみ受け取った場合
会社から弔電のみをいただいた場合は、お礼状のみを送付するのが一般的です。弔電を勤務先の福利厚生として受け取った場合は、担当者の方への口頭でのお礼でも構いません。
忌引き休暇を取得した場合は、代わりに対応してくださった同じ部署の方への挨拶、弔電のお礼を忘れずに伝えてください。
◇弔電と一緒に香典・供花などを受け取った場合
会社の福利厚生として弔電と香典、供花をセットでいただいた場合は、担当者へ口頭でお礼を伝えます。
社内の方から弔電と一緒に香典・供花などをいただいた場合は、お返しの品物を用意しましょう。
最近は、プリザーブドフラワー電報など、ギフト付き電報も人気があります。ギフト付き電報が届いた場合は、お礼の品物をお返ししなくても、マナー違反ではありません。ただし、「どうしてもお返しをしたい」という場合は、お返しの品物を用意してもよいでしょう。
部署単位で複数人から弔電と香典、供物などを贈られた場合、一人ひとりにお返しの品をお渡しすべきか、全体に対して用意すべきか迷うかもしれません。この場合は、その会社の慣習に合わせるのが無難です。
関連記事:
弔電と供花の両方をいただいたときのお礼はどうする?お礼状の文例や書き方を紹介
弔電のお礼状を作成する際の注意点
弔電のお礼状を初めて作成する際には、どのような点に気を付ければよいのか、悩んでしまう方も多いでしょう。そこで本章では、弔電のお礼状作成時の注意点として、押さえておきたい6つのことを紹介します。◇はがきや便せん、封筒はフォーマルなものを選ぶ
弔電のお礼状は通常、便せんと封筒、あるいははがきを使って送ります。その際は、装飾のないフォーマルなものを使用しましょう。
はがきや便せんは派手な絵柄のものを避け、無地や弔事に適したデザインを選びます。白地や薄いグレーなど、落ち着いた色がふさわしいでしょう。また、封筒を選ぶ際には、事務的な印象にならないよう、茶封筒は避けてください。はがきや便せんに貼り付ける切手も、弔事用のデザインを選びます。
なお、故人が生前に好きだった色、好みのデザインの便せんを、あえて使用する場合もあります。ただし相手との関係性、親しさの程度にもよるため、迷うようなら一般的な弔事用のデザインが無難です。特に会社の取引先、上司など目上の方に送る場合は、フォーマルな色柄のはがき、便せん・封筒を選択しましょう。
◇ボールペンや鉛筆は使わない
弔電のお礼状を手書きする際には、毛筆を使うのが最も格式が高いとされています。しかし、毛筆でのお礼状作成には手間がかかるため、現実的には対応できないケースが多いでしょう。そのような場合は、筆ペンや万年筆を用いても問題ありません。ただし、鉛筆やボールペンの使用は避けましょう。
また、昨今ではパソコンで弔電のお礼状を作成する方も少なくありません。パソコンでお礼状を作成しても失礼にはあたりませんが、手書きのほうがお礼の気持ちは伝わりやすいでしょう。
◇差出人の名前は喪主にする
弔電のお礼状の差出人は、喪主とするのが一般的です。そもそも、葬儀の主催者は喪主であるため、弔電の宛先も喪主になっているケースが大半です。
お礼状の差出人として、喪主ではない人の名前を使いたいときは連名にします。故人と家族ぐるみで親交があった方から弔電をいただいた場合は、喪主名に「親族一同」と添えるとよいでしょう。
◇忌み言葉の使用を避ける
弔電のお礼状のメッセージには、「忌み言葉」を使用しないようにしましょう。忌み言葉の例としては、以下のようなものがあります。
・不幸の重なりを連想させる言葉(重ね言葉):いよいよ、ますます、度々、次々、など
・不幸が続くことを連想させる言葉:再び、引き続き、追って、など
・不吉な言葉:四(死)、九(苦)、つらい、など
・生死を直接的に表現する言葉:生きていた、急死、死ぬ、など
・不幸が続くことを連想させる言葉:再び、引き続き、追って、など
・不吉な言葉:四(死)、九(苦)、つらい、など
・生死を直接的に表現する言葉:生きていた、急死、死ぬ、など
忌み言葉を使いそうになったときは、別の言葉で言い換えるとよいでしょう。忌み言葉と言い換え例については、以下の記事をぜひ参考にしてください。
関連記事:
弔電で避けるべき「忌み言葉」とは?宗教別の文例も併せて紹介
◇句読点は使わず、縦書きで書く
弔電のお礼状を書くときは、「、」や「。」といった句読点を入れないようにします。これは、会葬礼状などの冠婚葬祭に関わる文書の共通マナーです。句読点を使わない理由には諸説あり、「毛筆文化の名残」や「滞りなく式を進めるため」などと言われています。
また、弔電のお礼状は、縦書きで作成するのが一般的です。横書きではカジュアルな印象を与えてしまうため、弔電のお礼状にはふさわしくありません。親しい関係の方に出すお礼状以外は、縦書きで作成したほうが無難です。
◇故人の名前と略式のお詫びを記載する
弔電のお礼状の文面には、故人の名前を必ず入れましょう。故人の名前を記載しなければ、誰の葬儀の弔電に対するお礼なのかがわからないからです。その際、「故 ○○儀」のように、故人の名前のあとに「儀」を付けるのが、より丁寧な書き方とされています。
また、弔電のお礼状には略式のお詫びを一言添えましょう。前述のとおり、本来はお礼状の送付ではなく、相手方を直接訪ねるのが正式なお礼の伝え方です。「略儀ながら書中にて御礼申し上げます」のような一文を入れると、フォーマルな印象に仕上がります。
メールで弔電のお礼を送る場合
メールで弔電のお礼を伝える場合も、はがきや便せんでお礼状を送る際と、基本的な注意点は変わりません。忌み言葉や句読点を使わない点は、メールでお礼を伝える際も同様です。メールの件名は、弔電のお礼であることがわかるように記載しましょう。本文には、弔電をいただいたお礼の言葉、葬儀を無事に終えたという報告を入れます。
また、メールでのお礼は略式であるため、「略式ながら」などの文章を入れて、簡略化したお礼であることについてお詫びする旨を伝えてください。
連名での弔電のお礼状・お返しはどうする?
連名で弔電を受け取った際は、全員にお礼状を送るのが基本です。このとき、代表の方だけにお礼状を送ったり、誰かを一人だけ選んで送ったりするのはマナー違反です。複数人にお礼状を送る際は、送り漏れがないように十分に注意しましょう。一部の方のみ届けたり、一人だけ送り忘れていたりすると、のちに発覚してトラブルになるおそれがあります。
弔電のお礼状の文例【個人宛】【会社宛】
弔電のお礼状を書くときは、送る相手に合わせて適切な文面を考えましょう。参考として、「個人宛」と「会社宛」の2パターンの文例を紹介します。◇弔電のお礼状の文例【個人宛】
拝啓 このたびは 故 ○○儀の葬儀に際し ご丁寧な弔電を賜り 誠にありがとうございます
お心遣いに励まされ 滞りなく葬儀を執り行うことができました
生前のご厚情に深く御礼申し上げますとともに 今後も変わらぬご指導をいただきますようお願い申し上げます
本来ならお目にかかってお礼を申し上げたいところではございますが 略儀ながら書中にて失礼致します
敬具
令和○年○月○日
住所
喪主名
◇弔電のお礼状の文例【会社宛】
謹啓 皆さま方におかれましては ますますご健勝のこととお慶び申し上げます
このたびは 故 ○○儀の葬儀に際し ご鄭重な弔電をいただき ご厚誼に深く御礼申し上げます
おかげさまで葬儀も滞りなく済みましたことをご報告致します
略儀ながら書中にて 謹んで御礼申し上げます
謹白
令和○年○月○日
住所
喪主名
はがきや手紙、メールなどで弔電のお礼を伝えよう
身内の葬儀で弔電を受け取ったときには、葬儀から1週間以内にお礼状を出し、感謝の気持ちを伝えましょう。香典や供物をいただいていない場合は、相手に気を遣わせないため、基本的にお礼の品は不要です。弔電のお礼状を作成する際は、落ち着いたデザインのはがきや便せん、封筒を選び、毛筆や筆ペン、万年筆を用いて丁寧に書くと、きちんとした印象を与えられます。
そして、弔電のお礼状を出す前には、「差出人は喪主にする」「句読点を使わない」「縦書きにする」「略式のお詫びを添える」といった注意点を押さえておきましょう。メールで弔電のお礼を伝える際も、「忌み言葉や句読点を使用しない」などの基本マナーを守ることが大切です。
この記事で紹介した文例を参考にして、マナーを押さえた弔電のお礼状を作成しましょう。
電報サービス「e-denpo」の無料会員登録をしておくと、いざというときに弔電や供花を簡単に手配できます。お悔やみ電報は、即日で配送できる場合もあります。最短お届け時間の詳細、会員登録については、以下のページをご覧ください。
※供花の注文の際には、法人会員の登録が必要です。
【供花のラインアップ】
サイズ違いの供花もご用意しておりますので、詳しくは以下のページをご覧ください。
供花のラインアップを見る
【気持ちが伝わる弔電ラインアップ】
その他の弔電ラインアップは、弔電・お悔やみ電報ページからご確認いただけます。
弔電・お悔やみ電報TOPページ